 緊急司令!緊急司令!コードナンバー166。特殊行動隊「ブラックコブラ」のボウイ大尉に告ぐ。マウカ島のファラオ軍の要塞に、スーパーウェポン「GN-16B」が配置された。至急4名のスペシャリストと合流、完全作動開始前に要塞に進入し、これを破壊せよ。小火器のみ合流地点で支給するが、その他必要なものは現地で調達されたし。以上。(マニュアルより抜粋)
緊急司令!緊急司令!コードナンバー166。特殊行動隊「ブラックコブラ」のボウイ大尉に告ぐ。マウカ島のファラオ軍の要塞に、スーパーウェポン「GN-16B」が配置された。至急4名のスペシャリストと合流、完全作動開始前に要塞に進入し、これを破壊せよ。小火器のみ合流地点で支給するが、その他必要なものは現地で調達されたし。以上。(マニュアルより抜粋)
FINAL ZONE
日本テレネットより1986年5月に発売
Story
 緊急司令!緊急司令!コードナンバー166。特殊行動隊「ブラックコブラ」のボウイ大尉に告ぐ。マウカ島のファラオ軍の要塞に、スーパーウェポン「GN-16B」が配置された。至急4名のスペシャリストと合流、完全作動開始前に要塞に進入し、これを破壊せよ。小火器のみ合流地点で支給するが、その他必要なものは現地で調達されたし。以上。(マニュアルより抜粋)
緊急司令!緊急司令!コードナンバー166。特殊行動隊「ブラックコブラ」のボウイ大尉に告ぐ。マウカ島のファラオ軍の要塞に、スーパーウェポン「GN-16B」が配置された。至急4名のスペシャリストと合流、完全作動開始前に要塞に進入し、これを破壊せよ。小火器のみ合流地点で支給するが、その他必要なものは現地で調達されたし。以上。(マニュアルより抜粋)
ゲームの概要
このゲームは、プレーヤーがボウイ大尉になって、コマンド部隊に届く緊急指令に従い、ミッションをこなしていくアクションゲームである。ゲームとしては、アーケードの「怒」のようなタイプである。ちなみにストーリーとしては、「敵ファラオ軍が、南海の島マウカ島にある要塞にスーパーウェポン"GN-16B"を配置した。これはまだ完全に動作していないが、もし動き出せば我が軍は大変な被害を被るので、その前になんとしても島に潜入して破壊してしまえ」というものだ。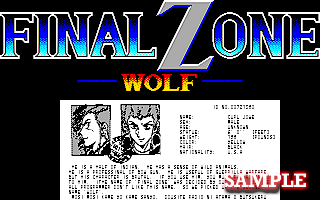
ボウイ大尉には、4名の優秀の部下が与えられる。その部下はおのおの得意の武器があり、潜入する島の地域によってメンバーを選択して戦う(ただし、選択しないで一人で行くことも可能)。武器・弾薬類は、最初にもっている小火器以外はすべて現地で調達する。
ゲームの開始
ゲームを起動すると、2,3秒で「グゥワーン」という鐘の音とともに「WOLF TEAM」のロゴが表示される。当時、これほど高速に起動するDOSは珍しく、驚いた記憶がある。しばらくディスクがアクセスすると、バックミュージックとともにゲームのストーリーをデモを交えて紹介する。また、このデモが映画を見るような展開になっていて、新鮮であった。
会話のデモが終了すると、その面を戦うメンバーを選択する。メンバーは以下の4人である。
カール・ジョー・・ボウガンの名手で、性格がひねくれている。ボウイ大尉につっかかってくる。インディアンの血を引く。
メンバーを選択すると、ゲームが開始される。ゲームは縦スクロールのアクションゲームで、[2][4][6][8]で移動、[X]で手榴弾、[SP]で射撃、[Z]キーでフォーメーションの変更である。スクロールは強制ではなく、自分で進んでいく方式だ。敵がウヨウヨと登場するので、銃や手榴弾で敵を倒していく。画面上部には自分の体力があり、ダメージを受けると減少し、ゼロになるとゲームオーバーである。ただし、他のメンバーは途中で死んでもゲームオーバーにはならず、次のデモシーンでは出てこなくなるだけだ。
こうしてその面の最終ラインまでいき、敵を殲滅すると一面クリアとなる。
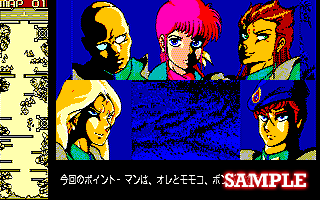
なにかキーを押すとゲームが開始される・・・のがそれまでのゲームだったが、いきなりゲームが始まらずにメンバーとの会話デモが始まる。この会話は面と面の間に必ず存在し、ミッションの内容やボウイ大尉と部下のやり取り、彼らの過去などが語られ、1つの物語を形成している。しかも、これをまともに見るとかなりの長さである(もちろんスペースキーでキャンセルはできる)。いままでのアクションゲームでは、ゲームを開始すれば単にゲームが始まるだけであった。ストーリー性をゲーム中に求めるということはほとんどなかった(ストーリーはマニュアルで述べられるだけであった。しかもストーリーといってもあまりゲームと関係ないような、後から取ってつけたようものだったである)。また、ロールプレイングゲームにしても、アドベンチャーゲームにしても、ゲーム中のストーリーは存在しても、アニメーションっぽい絵に口パクをしながら、デモのような形式でストーリーを述べるという形式はなかった。現在ではこの形式は当たり前であるが、当時では、非常に画期的なことであった。
リン・モモコ・・ナイフを使う東洋系の美女。実はストーリー上、キーになってくる。彼女が面の途中で死ぬと、ストーリーが多少変わる。
ランディ・ハンセン・・バズーカを使う大男。昔ボウイ大尉と行動をしていた。
ダコタ・ボンバー・・クールな男で、マシンガンを使ってするので近距離に強い。
このゲームは弾薬の個数が決まっているので、途中で武器を拾ったり、弾薬を拾わないと、弾切れになりやすい。考えて使うことが必要である。面の途中にはライフル、ナイフ、バズーガ、ピストルなどが落ちているのだが、画面上には見えないようになっていて、ある場所の上を通ると自動的に拾うようになっている(けっこうシンドイのだが)。
フォーメーションというのは、メンバーを選択したときに、そのメンバーが自分を中心にどのように動くのかというもので、たとえばジグザグ型を選択すると、テンキーで大尉を動かすとメンバーもそれに合わせて左右に動きながらついてくるのだ。ただし、下手なフォーメーションを選択すると、メンバーが障害物にひっかかって、自分が先に進めなくなってしまう。このような場合、フォーメーションを変更し、自分がメンバーのところまで戻ってやらないと、メンバーは引っかかったままとなってしまう(なんとも間抜けだ)。フォーメーションは12種類あるが、ものすごい複雑な形をしていて、本当にこんな複雑な動きをメンバーがしているのか疑問である。ちなみにX1版では、もっとシンプルなフォーメーションになっている。
スクロール画面
ファイナルゾーンの特徴として、8色カラーを使った縦スクロールが上げられるだろう。この時期まだまだ8色カラーを使ったスクロールゲームは少なく、この美しく緻密な画面が話題になったものだ。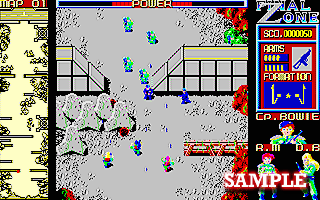
面は市街地から水中、森林へと変化する。キャラクターは水中ではきちんと肩まで水に浸かるという凝りようである。スクロール単位は16×8ドットで、これは後の「イース」などに見られるスクロールするロールプレイングゲームと同一の単位である(8ビット単位だと内部処理がしやすいため)。スクロールが多少荒く感じるが、これは「イース」などのような差分スクロール(変化しない場面はそのまま書き換えない)はしておらず、単純にSRのパワーにモノを言わせて、すべてのパターンをVRAM上に転送しているからしかたないだろう。
当時としては、フルグラフィックのカラーでスクロールするゲームが非常に稀であったため、少しくらいガタついていてもそれほど気にならなかったし、それがゲーム性を損なうことはなかった。
デモと音楽の原点
後に日本テレネットの代名詞となる「デモと音楽」であるが、原点はこのファイナルゾーンにあるだろう。ゲームを起動するといきなりロゴが表示される。そのあと、長いデモが始まる。当時これほどまでに映画を意識して、長くてカッコいいデモが挿入されたゲームは88では前例がほとんどなかった(このゲームが元祖といってよいだろう)。面ごとのビジュアルシーンでは、ボウイ大尉と仲間とのやりとり、モモコと敵ウェルダー大佐との関係などが、プレーヤーそっちのけで進んでいく。この「そっちのけ」が重要である。プレーヤーを無視し、映画のように完全にこちらが受身になって物語が進んでいってしまうのだ。エンディングも見事だ。映画のようにスタッフ名が表示されながら、哀愁が漂うメロディが流れ、そしてゲーム後のストーリーを垣間見せるようなグラフィックが、少しずつ動いていく。
音楽も実にすばらしい。恋瀬氏(佐藤氏)の音楽は、哀愁漂うものから、かっこいい戦闘曲まで実に幅広く作られている。特にオープニング曲、エンディング曲はかなりの長さで、メロディや構成も一般の音楽、当時流行していたカシオペアやスクウェアのようなクロスオーバーミュージックを彷彿とさせるものであった。また、FM3音にPSGドラムを加えたはじめて音楽を作ったものだと思う。PSGドラムで、強引ともいえるドラム、バスドラム、シンバルなどの表現は、このゲーム以降、OPNを使う上でスタンダードなものになっていった。ちなみにあのシンバルの音を考え出したのは、恋瀬氏だと思われるが、よく考えたものだと感心する。
また、面の途中で曲が切り替わるのもたぶんこのゲームが初めてである。ボウイ大尉のエネルギーが減少してくると「ピンチのテーマ」に曲が変更されるのである。まるで「ウルトラマン」のカラータイマーが赤になったときに曲が変わるような展開で、なかなか緊迫感が出て良かった。
このゲームで成功した「ゲームにふんだんにデモを入れる」という手法は、後のテレネットの代名詞的な存在になり、ますますパワーアップしていくことになる(一部ではパワーアップしすぎて、ゲームよりデモの方に力が入っているという説さえでてしまったが・・)。

また、「ミュージックモード」を用意したゲームも、これが初めてだったと思う。音楽のすばらしさをテレネット内部でも感じていたのだろう。[F5]キーをデモ中に押すとミュージックモードに入る。当時はゲームの音楽などは世間には全く認知されていなかったし、鑑賞するということ自体、あまり考えていなかったと思うのに、きちんとこのようなモードを挿入するあたり、音と映像のこだわりが感じられる。
ゲームの欠点
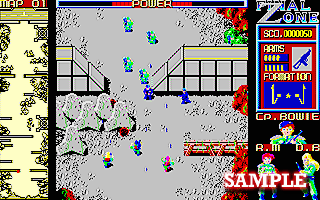 このゲームは、アクションゲームとしてはなかなかよくできていたと思うのだが、メンバーの動きだけは問題を残した。フォーメーションは12種類もあるが、どれもそれほど有効に思えないし、実際に他のメンバーがあの複雑なフォーメーションを描いているとは考えにくい。現にX1版ではフォーメーションが減ってしまった。それに、仲間が引っかかって前に進めないというのもおかしい。これでは仲間は単なるお荷物な存在である。実際に、最も簡単な攻略法は仲間をつけずに自分一人ですべての面に挑むことである。なんとも皮肉なことではないか。
このゲームは、アクションゲームとしてはなかなかよくできていたと思うのだが、メンバーの動きだけは問題を残した。フォーメーションは12種類もあるが、どれもそれほど有効に思えないし、実際に他のメンバーがあの複雑なフォーメーションを描いているとは考えにくい。現にX1版ではフォーメーションが減ってしまった。それに、仲間が引っかかって前に進めないというのもおかしい。これでは仲間は単なるお荷物な存在である。実際に、最も簡単な攻略法は仲間をつけずに自分一人ですべての面に挑むことである。なんとも皮肉なことではないか。
さらに、武器の調達はゲームの途中で行いのだが、全く落ちている武器が見えないというのも、ちょっと不親切だった。また、ゲームのクリア条件も明示されていないので、面の最後までいったものの、どうやったらクリアになるのか、最初はみな迷っただろう。
最後に
ファイナルゾーンは、後に主流になるドラマチックロールプレイングゲームの先駆けといえる存在だと思う。これは、アニメーションの絵、ゲーム中のデモの挿入、映画のようなストーリー展開、キャラクターの口パクなどに見ることが出来る。
ファイナルゾーンは88のゲームで、映画的手法を取り入れた初めてのゲームであり、後に与えた影響は大きなものであった。
このゲーム以降、徐々にSR専用のゲームが増え始め、しかも内容(ストーリー)を重視する傾向のゲームが増え始めるのは確かである。このストーリーを表現するために、グラフィック、デモ、そして音楽という要素が重要になり、ディスク枚数もどんどんかさむ傾向になっていくのである。
ファイナルゾーンを作った人
ファイナルゾーンの制作の中心人物は、後にウルフチームの取締役となる秋篠雅弘氏である。秋篠氏は、高校時代は生徒会に属し、8ミリに凝って大学では映画研究会に所属していた。パソコンとの出会いは意外と遅く、大学時代に8801mkⅡを購入したのが最初。もともと映画好きの氏は、字幕とかワープロを使いたいという動機からパソコンを購入した。買ってはみたものの、市販のワードプロセッサがあまり使えなかったため、自分で漢字をプットしたくてまずBASICを覚えたりしたらしい。
彼は東京理科大学卒業後、ファイナルゾーンを担当していた林浩樹氏などとともに株式会社ウルフチームを設立し、テレネットから分離することになる。
参考文献:月刊テクノポリス86年11月号P.106
ファイナルゾーンに関連するすべての画面写真、パッケージ写真の著作権は株式会社日本テレネットに帰属します。
秋篠氏がテレネットに出会ったきっかけはアルバイト雑誌のフロムAをみたことである。このときはテレネットはまだ「アメリカントラック」が発売される前なので、設立してから間もないことであった。小遣い稼ぎの軽い気持ちでバイトした秋篠氏であったが、すぐに大きな仕事をまかされることになった。それまで本格的なプログラムを組んだことがない秋篠氏だったが、85年の8月に「ファイナルゾーン」の企画を開始、原作を作成していった。秋篠氏は、原案と88のプログラミングを担当したらしい。まずは人型の戦場タイプのシューティングゲームにしようと思ったという。それまで人型のシューティングゲームはあまり発売されていなかった。また、ゲームにストーリー性を持たせて、他のゲームとの差をつけようとこのときすでに考えていたらしい。
具体的な仕事は、まずスクロールの重ね合わせのデータから始まった。ファイナルゾーンは、少し上からみた画面になっているため、キャラクターの存在に3段階のプライオリティをつけていくのが大変だったそうだ。またキャラクターパターンが非常に多いため、それを少なく見せるのにも注意したらしい。また、林の中に入る擬似スクロールは16ビットでなくては難しいと言う結論に達したらしいのだが、それをなんとか8ビットマシンで表現できたということも自慢の1つのようだ。
秋篠氏の写真月刊テクノポリス86年11月号より引用